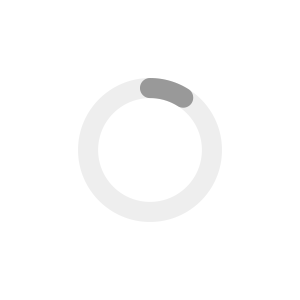戦利品のオメガ
BLオメガバース
2025年05月02日
公開日
公開日
3.3万字
完結済
完結済
「褒美として、戦利品のオメガを将軍に下げ渡す」
将軍アルスーンは、自国が滅ぼした国のΩを下賜された。王に疎まれていると察していたアルスーンは、孕まないとわかっていながら欠陥Ωのシャオティエン王子を大人しく迎え入れる。伴侶という形は取ったものの、相手が望まないのに肌を合わせることはできない……そう考えていたアルスーンだが、シャオティエンから「あなたはわたしの運命です」と告げられたことで状況が変わり始める。
第1話