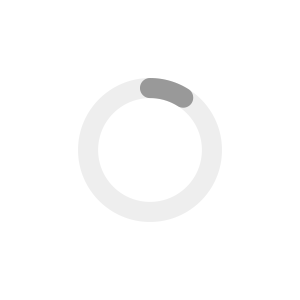大逆転、関ヶ原! ~小早川秀秋、難波の夢を露と落とさず~
歴史・時代戦国
2025年07月18日
公開日
公開日
6.3万字
連載中
連載中
目が覚めたら、そこは夢の中。
自分で言っていて意味不明だが、俺は戦国時代の関ヶ原に居た。
だったら、やる事は一つ!
俺は小早川の姓を持つ一人として、家康を討つ!
陣太鼓を鳴らせ! 長年の夢を夢の中で実現させるチャンスだ!
うん、やっぱり言っている意味が解らないぞ?
早く目を覚まして、仕事に行かないと……。
あれ? 目が覚めたら夢の中だったんだよな?
寝てるの? 起きてるの? ますます解らなくなってきたぞ?
序章 問い鉄砲