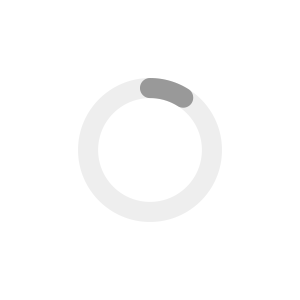ウエスタン信長公記
歴史・時代戦国
2025年08月22日
公開日
公開日
10.2万字
完結済
完結済
天文十六年(1547)、元服を終えて初陣を控えた織田信長は、産まれたときに一度死んで生き返ったという事実から母親に疎まれ、馬術や水練、相撲だけでは満たされない鬱屈した少年時代を送っていた。
その彼の前に、馬と話して盗む異人が現れる。イサクァという名前の異人は、アメリカ大陸から奴隷としてスペインの船に乗せられ、ポルトガルの船に売られて種子島に流れ着いたネイティブアメリカンであった。一族に伝わる〈悪霊〉退治が使命だというイサクァは、少年信長のことを一度死んだ人間は戦いの場では決して死なない〈歩む死〉であるからと、「キモサベ」と呼んで自分の手伝いをするように求めてくる。
その誘いを一度は断ったものの、初陣をイサクァの風を読む能力に助けられた信長は、次第に彼に影響されていき、インディアンの伝統的な格好や破天荒な行動を真似るなどして「大うつけ」と噂されるようになっていく……
少年時代の信長がインディアンの呪術師の相棒となり、様々な冒険に挑戦する浪漫譚、ここに始まる!
序章
第1話 天正九年 安土城にて