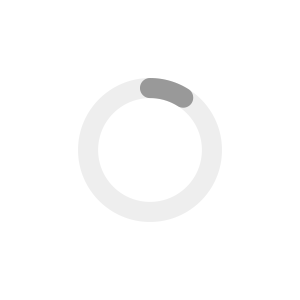【怪文書】〈百合〉はなぜ文化になったのか──ジェンダー・メディア・市場の交差点で
文芸・その他雑文・エッセイ
2025年06月19日
公開日
公開日
1.7万字
連載中
連載中
本論文は、「百合」と呼ばれる女性同士の親密な関係性を描いた文化的ジャンルが、いかにして日本社会において成立し、発展してきたのかを多角的に考察するものである。百合文化は友情と恋愛のあいだに存在する曖昧な情動を表象しながら、少女小説や漫画、アニメといったメディアを通して独自の市場と支持層を形成してきた。
論文はまず、百合文化の歴史的源流を大正期の「エス」文化や少女文学に求め、戦後の少女漫画を経て現代のメディアミックス作品に至るまでの系譜を整理する。その上で、ジェンダー研究やメディア論の観点から、百合がなぜ商業的にも文化的にも成立しうるのかを分析する。
さらに、同人文化やSNSを通じたファン主導の創作、クラウドファンディングによる作品支援の実態を踏まえ、百合が単なるサブカルチャーにとどまらず、グローバル化の文脈でも存在感を強めている現状を論じる。最後に、表現倫理や多様性の観点から、現代における百合表象の課題と可能性を展望する。
本稿は、百合という文化が、性別や恋愛観に対する既存の枠組みを問い直す表象空間として、今後さらに重要な意味を持ちうることを示唆するものである。
第2章 歴史的背景と萌芽